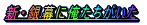・レイバーネットTV(11/13)
・あるくラジオ(10/10)
・川柳班(11/22)
・ブッククラブ(10/12)
・シネクラブ(9/1)
・ねりまの会(10/12)
・フィールドワーク(足尾報告)
・三多摩レイバー映画祭
・夏期合宿(8/24)

・レイバーネット動画
●「太田昌国のコラム」第96回(2024/11/15)
●〔週刊 本の発見〕第368回(2024/11/21)
●「根津公子の都教委傍聴記」(2024/11/14)
●川柳「笑い茸」NO.157(2024/9/26)
●フランス発・グローバルニュース第14回(2024/10/20)
●「飛幡祐規 パリの窓から」第95回(2024/9/10)
●「美術館めぐり」第4回(2024/10/28)
★カンパのお願い
■メディア系サイト
原子力資料情報室・たんぽぽ舎・岩上チャンネル(IWJ)・福島事故緊急会議・OurPlanet-TV・経産省前テントひろば・フクロウFoEチャンネル・田中龍作ジャーナル・UPLAN動画・NO HATE TV・なにぬねノンちゃんねる・市民メディア放送局・ニュース打破配信プロジェクト・デモクラシータイムス・The Interschool Journal・湯本雅典HP・アリの一言・デモリサTV・ボトムアップCH・共同テーブル・反貧困ネットワーク・JAL青空チャンネル・川島進ch・独立言論フォーラム・ポリタスTV・choose life project・一月万冊・ArcTimes・ちきゅう座・総がかり行動・市民連合・NPA-TV・こばと通信
|
|
|
ログイン |
|
情報提供 |
|
|
|
Status: published View |
●木下昌明・映画の部屋 『息子のまなざし』(2004年1月23日掲載)少年犯罪―被害者と加害者の接点を問う
『息子のまなざし』ラストシーンの意味
わたしはダルデンヌ兄弟の『息子のまなざし』にすっかり魅せられた。このところ映画好きの友人に出会うと、つい「『息子のまなざし』をみた?」とあいさつがわりに聞くようになったが、それはひとえに『週刊金曜日』(12月19日号)に、この映画を「本年度ベストワン」などと普通ならつけないようなタイトルをつけてしまったことにある。それに反し、年末にみた『週刊文春』(12月18日号)のシネマチャートをみると、品田雄吉、斉藤綾子が星三つと評価が高いのに、中野翠とおすぎは、ともに星一つで「ガラス越しに見ている感じがつきまとう」とか「他の人に観なさいと進めることは出来そうにもありません」と低く、評価はわかれていたが、この中野とおすぎの酷評に驚かされた。また、筑紫哲也は『週刊金曜日』の同じ号やテレビ番組「ニュース23」でいろんなお正月映画を取り上げていたが、この映画は全く話題にしていなかった。これはひどいと思ったのだが、新年になってやっと『朝日新聞』(1月6日号)と『毎日新聞』(1月7日号)で評価しているのが目についた。特に『朝日』の「静かに深く、『人間』を問う」と題した秋山登の批評には力がこもっていて共感できた。それでも物足りないとおもったのは、どれもわたしの重視した<労働>の観点に光をあてたものがなかったからだ。かくいうわたしのそれも、紹介批評的なもので、もっと問題を鮮明にあぶりだせていなかったことが心残りとなった。特にラストシーンについては「見事である」としか書かなかった(書けなかった)。それは映画をみていない観客に、どんなふうに「見事」なのか自分の目で確かめてもらいたかったからであるが、ラストの「見事」さをどう受けとめたかをいう問題を語らなければこの映画の核心を批評したことにはならない。そこで前回の批評を補うためにももう一度書くことにする。それによって<労働>の問題ももっとみえてくるとおもうのだ。
<ダルデンヌ兄弟の独特な手法>
この映画は、主人公が何をみて、何をおもって、どんな行動にでるのか−−を観客が漫然とみるのではなく、画面を観察し、考える(考えさせられる)、そんなつくりになっている。主人公とは、ベルギーの地方都市・ある職業訓練所の木工クラスで教える指導員オリヴィエのこと。その息子を殺した少年が突然入所してきたので、被害者の父のかれが加害者の少年にどのように接していくのかの4日間がドラマの骨子となる。
まず映画の特徴からふれていくと、映像は少しも説明的でなく(だから観客の想像力をかきたてる)、音楽は一切使っていないこと(作り手が、あるシーンをムード的に強調するのを自ら禁じている)、それに登場人物は必要最低限の会話しかしないし、喜怒哀楽の感情も極力抑えられていること(言葉や感情よりも「まなざし」が物を言っているのだ)。さらに、撮影にはハンディカメラを駆使しているが、カメラは主人公の背中にはりつくようにして肩ごしにとらえるので、その視野は、かれがみたりみられたりする視線の範囲に限られている一人称的な映画といえよう。この手法によって、日頃ハリウッド映画をみなれている観客は違和感をおぼえるだろうし、カメラのぶれで船酔いしそうになるひともでてこよう。これはダルデンヌ兄弟が前作『ロゼッタ』(99年)でも用いた手法なので、その時わたしは船酔いしそうになったが、こんどは心がまえができていたのでなんともなかった。しかし、この手法はやはり一考を要するようにおもえた。生理的不快が観察意欲をそぐからだ。だが、そうはいっても、カメラが主人公の行動によりそうことによって、かれの不安や怒りや動揺などの内面の視覚化が容易となるのも確かなのだ。
たとえば、トップシーンでオリヴィエが少年フランシスの願書をみて、木工クラスに入れることを拒む。そのあと窓ガラスごしに少年の後ろ姿を目で追ったり、事務所へのぞきにいったりと不審な挙動シーンがつづく。この時点では、まだ少年がかれの幼かった息子を殺した加害者だと知らされていないから主人公の挙動に訳がわからずふりまわされていら立つ観客もでてこよう。そういったことが、中野やおすぎの酷評とつながったといえなくもない。それでも、よく観察すると、その意味がわかってくる。かれは動揺しつつもどんな「やつ」なのか好奇心でいっぱいになり、そこから相手を知りたいという感情が芽ばえ、かれの奇妙な行動がはじまる。そこがダルデンヌ兄弟の腕の見せどころでもある。
<主人公の不可思議な行動>
つぎに、オリヴィエがアパートに帰宅してからの場面−−かれが食事の支度をしていると、別れた妻がひさしぶりに訪ねてくる。彼女はほかの男性の子を宿したので人生をやり直したいと告げる。かれは彼女に背を向けたまま聞いている。やがて車で帰ろうとすると彼女をかれが追ってきて、なぜ今日訪ねたのかと問いただす。彼女は自分のことしか念頭になかったので、検査で妊娠とわかったから、と答えるが、かれのほうは少年の出所とぶつかったことが気になったのである。ここに両者のおもいのズレがとらえられている。だから、ここからのオリヴィエの飛躍が興味ぶかい。かれは少年を自分のクラスにひきとる決意をするからだ。なぜ別れた妻の再婚話と少年をひきとることがここで唐突につながるのか−−この一見無関係にみえる事実が、オリヴィエの内面の深層でつながり、それが人間の不可思議さというリアリティーをもって迫ってくる。映画は、この夫婦が、なぜ離婚したか、一切描いていない。それでいてオリヴィエの言動をみていると、寡黙な職人気質で、喜怒哀楽を表にださない性格がみえてくる。悲しみに打ちひしがれた妻には、そんな夫が耐えがたい存在にみえたろうことは推察できる。それでも、かれらはいままで息子をうしなったことでは同じ「傷痕」を共有できていた。ところが一方が人生をやり直すとなると、二人のあいだにあったバランスが崩れ、かれのほうは二重の喪失感を味わう。その一瞬の空虚なおもいが、かれの思考とはうらはらに、何か別のよりどころを求めて少年の受け入れに走らせる。なんという不条理か。それでもそれは大いにありうる人間の、どうにも制御できない矛盾した行動である。まるでバケツの水が大量にこぼれたのであわてて新しく水をくもうとするように。このずっとあとのシーンで、元妻がかれの行為を「狂気のさたよ」となじって「なぜ」と問うても、かれには「わからない」としか答えられない。
つづけて翌日、オリヴィエが彼女の働いているスタンドを訪ねるシーンも興味ぶかい。そこでかれは彼女と会う前に車の中でたばこを吸う。この間がいい。そこにためらいもある。このあとかれは昨日いえなかった彼女に子どもができたことを喜んでみせる。ところがだ。その舌の根も乾かぬうちに「あいつが出所した」と彼女の胸をえぐるような言葉をなげかける。本当はこの一言がいいたくてわざわざやってきたのである。それはこれまで共有していた「傷痕」を忘れて別の道を歩もうとする彼女への「忘れるな!」のメッセージでもある。たちまち彼女の表情は凍りつく。言わなくてもいいものをあえて言ってしまうかれ(人間)の愚かさは、ほかでもない「傷痕」といえどもそれを共有することで人間関係をつなげていきたいとする気持ちの表れである。この微妙な心理がわかるのは、そぎ落とした簡潔な表現によって一つ一つのシーンのつながりがよくみえてくるからである。そこに緻密な構成と巧みな演出がある。一方、オリヴィエの革製の幅広い腹帯について、「背中が痛む?」と元妻が尋ねるところや、少年たちの木材かつぎのハシゴ訓練のところに事故を連想させ、いまだ癒されないかれの内面の象徴をみることもできる。
また、印象的なのは、オリヴィエの使う大工道具−−ノミやナイフやヒモなどは、単なる道具のそれではなく、かれの内奥の殺意を観客の意識にひらめかせる。それらは腹帯とは反対に攻撃性をおびている。まるで内にひめた感情が道具にのりうつったかのようだ。その典型例がロープのシーンである。かれが少年と二人で材木とりに車で向かう朝、ロープをていねいに束ねているところ、それを車のトランクに入れるところ、ラストでトランクからロープをとりだすところ−。まるでサスペンスドラマのようにロープがロープ以上の存在感をもってせまってくる。わたしはロブグリエの反小説(アンチロマン)『嫉妬』を思い出した。それは壁を這うトカゲや髪を梳る音などを精緻に描写したものだ。実はその描写の背後に妻の不倫を疑う夫がいて、それらはかれの視線によってとらえられた<物>であり、嫉妬にかられた夫の内面をくぐりぬけたシュールな現実とわかる。といっても映画の大工道具は復讐の道具に変質するわけではなく、あくまでも大工道具のままである。
<二人を結びつけているもの>
さて、『息子のまなざし』でもっとも重要なのは、主人公と少年との関係性をとらえたところ。映画の展開にともなって、二人の関係が距離を縮めていくからだ。それは<労働>に関する場面である。といっても、ここでの<労働>は、木工作業に関する訓練などその手順のイロハを教える側と教わる側との関係を描いたシーンをさす。その問題の一つのケースとして、わたしは前回の批評で、少年が指導員の目測の正確さに驚きそれを確認する路上のシーンについてふれた。
そこでつぎのステップをみてみる。それは主人公が少年に自分用の大工道具入れの木箱をつくらせるシーン。これが少年にとってのはじめての<ものつくり>となる。オリヴィエの指示にしたがって少年がヤスリをかけ、寸法をはかり、クギを打ち、ヒモをつけて完成させる。少年に自信をつける最初の成果となる。それが指導員の後ろから降りていく階段シーンで示される。少年は指導員と同じように右肩に道具入れを−−新しい木箱をかけているからだ。
このように実地教育をとおして二人の関係はいや応なく縮まっていく。それがいっそう縮まるのは、翌日、二人だけで車に乗って材木をとりにいく後半のシーンである。途中、店に立ちよって食事中、少年がふと「後見人になってくれ」とかれに頼むところ。これにオリヴィエはいいよどむ。かれは、指導員として一人前の大工にするために、少年にはきちんと仕事を教えているが、かれ自身少年を受け入れたわけではなく、名前も「お前」としかよばず、握手もしないで、意識的に距離をおきつづけてきた。それが思いもよらぬ頼みに一瞬とまどうわけだ。ところが少年にすれば、仕事を習っているから当然のようにかれとの関係を深めようとする。この関係の縮まり方が絶妙である。そんななかで、父親不在の少年の境遇も浮かびあがってくる。
しかし、指導員にとっては、予測しないうちに相手が距離を縮めてくることは耐えがたい・許せないことだった。ついにかれは材木置き場で「お前が殺したのはおれの息子だ」と少年に告げる。少年はとっさに森に逃げるもののすぐかれに取り押さえられる。かれは馬乗りになって少年の首を絞める。そこにすべてを奪った者への憎悪が凝縮している。やがて首から手をはなし、かれはあえぐ。それを少年は下からじっとみつめる。
わたしが「見事」というラストシーンはここからである。一人で引き返した主人公は、車に木材をつんでいく。するとかれの視線の向こうに少年が突っ立ったままかれをみているではないか。かれはそれを無視していると、少年が近寄って自分も木材をとって二人はしばしにらみ合う。この間全くせりふはなし。かれは木材にシートを覆うと、少年がそばによってそれを手伝う。主人公が車からロープをとりだしても、少年は何のためらいもなくシートを押さえ、主人公がその上からロープを巻きはじめる。そしてジ・エンド。
これをあっけない幕切れというひとがいる。また評者によっては、そこに「許し」をみるひともいる。しかし、わたしがこのラストに目をみはったのは、むしろそうした意味ありげな解釈が成り立たないことによってだ。争った二人が無言のままで、釈明することも許し許されるといった「儀礼」的な身ぶりもなく、それでいてなおそこでは結びついている。結びつけているのはほかでもない一つの作業の共有なのである。この少しもドラマチックではない光景が、ここでは光り輝いている。二人の距離がこれによってさらに縮まるだろう。言葉はなくとも、人間と人間とを結びつけるふしぎな力の原初的な姿がそこにとらえられていた。
しかし、それによって殺人が決して許し許されることにはならない。少年院で5年の<刑>をへてこようとも、被害者家族の苦しみは癒されるものではない。それは生涯消えない「傷痕」となって二人の間に残り続けるだろう。殺人の被害者(家族)と加害者がどんなに許し許されても、最後の一線は越えられないし、また越えてもならないものだろう。その上で、互いに相手も同じ人間として認め、その関係−−どんなに縮まっても距離のありつづける関係−−を保ちつづけることが大切ではないのか−−と。このようにして少年犯罪者を受け入れていく社会の必要をダルデンヌ兄弟は問うている。こんにち日本でも起きている少年犯罪を考える上で、この作品は示唆にとんでいる。
『息子のまなざし』について、一つ一つのシーンをみていけば、語りつくせないほど問題がいろいろからみ合ったように出てくるが、とりあえずここで筆をおくことにする。たまにはこういう映画をみて、映画というものが単なる退屈しのぎの「娯楽」でないことも知ってほしい。映画は人生社会を観察し、考える(考えさせられる)ための豊かな機会をあたえてくれる素材でもあるからだ。
*この原稿は「レイバーネット日本・ウェブサイト」向けに書き下ろしたものです。同映画は東京・渋谷「ユーロスペース」で上映中。著者への感想はこちらへ。
Created byStaff. Created on 2005-09-04 20:40:22 / Last modified on 2005-09-04 20:47:31 Copyright: Default