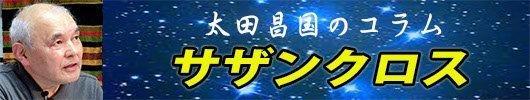●第27回 2019年1月10日(毎月10日)
第一次世界大戦終結から百年後に観た映画
 なぜか見逃してきていたジャン・ルノワール監督の『大いなる幻影』(フランス、1937年/写真)を、年明け早々デジタル修復版でようやく観ることができた(東京池袋・新文芸坐、1月3日)。昨年、「ロシア革命百年」をめぐる連続講座を行なって、20世紀以降の現代史において第一次世界大戦が持つ意味の大きさを改めて再確認していた。また昨年11月11日には終戦から百周年を迎えたとして、当時は「敵・味方」に分かれて戦った各国の首脳がパリに集まって記念行事が開かれたと知って、航空機・潜水艦・毒ガス・戦車・機関銃などの新兵器が投入され、兵士・民間人合わせて1,500万人の死者を出したといわれる戦争の惨劇は記憶され続けているのだと思った。この第一次大戦を背景にして描かれたルノワールの名高い〈反戦映画〉を見逃してきたことを悔やむ気持ちはいっそう募っていた。
なぜか見逃してきていたジャン・ルノワール監督の『大いなる幻影』(フランス、1937年/写真)を、年明け早々デジタル修復版でようやく観ることができた(東京池袋・新文芸坐、1月3日)。昨年、「ロシア革命百年」をめぐる連続講座を行なって、20世紀以降の現代史において第一次世界大戦が持つ意味の大きさを改めて再確認していた。また昨年11月11日には終戦から百周年を迎えたとして、当時は「敵・味方」に分かれて戦った各国の首脳がパリに集まって記念行事が開かれたと知って、航空機・潜水艦・毒ガス・戦車・機関銃などの新兵器が投入され、兵士・民間人合わせて1,500万人の死者を出したといわれる戦争の惨劇は記憶され続けているのだと思った。この第一次大戦を背景にして描かれたルノワールの名高い〈反戦映画〉を見逃してきたことを悔やむ気持ちはいっそう募っていた。
『大いなる幻影』が描くのは、ドイツの古城に設置された捕虜収容所内のフランス人、イギリス人、ロシア人たちの日常の姿、とりわけ捕虜になったら脱走すればよいと考えて、失敗を重ねながら脱走の企てを諦めないフランス人将校のあり方である。容貌魁偉な収容所長のドイツ人将校は貴族の出自なのだが、敵方の捕虜の中に貴族を見出すと親愛の情を示さずにはいられない。階級差へのこのこだわりに着目したのは、王侯貴族が国を超えて姻戚関係を結んでいた古くからのヨーロッパ史へのさりげない風刺なのか。ともかく、対立と憎しみを描いて完結しがちな「戦争映画」に、融和と友愛の挿話をちりばめた物語構成に、ルノワールのしたたかな意図を感じた。

別な側面からも第一次大戦を振り返ってみよう。一昨年に100周年を迎えた1917年のロシア革命は、もともと、ツァーリ帝政下で第一次世界大戦に動員された農民兵士たちの戦争拒否の動きを主要な動因として始まった。戦争を拒否するどころか、軍隊そのものを否定する、つまり兵士としての自己を否定するものとして始まった10月革命。それは、300年間続いてきた王制の廃絶にまで行き着いた。その後のソ連が辿ることになる過程が、世界各地の少なくない人びとが抱いた社会革命に対する夢と希望を踏みしだくものであったことは事実だが、革命の初心として実在した民衆レベルでのこの思いの重要性は、これからの人類社会の指標として救い出されるに値すると私は思う。
『大いなる幻影』と『まぼろしの市街戦』はフィクションだ。ロシア兵士の動きは現実の出来事だった。世界大戦を、よくあるように「戦史」として描いて導き得る教訓もあるだろうが、虚実交えて「反戦」の観点から眺めた時にどんな世界像が、どんな戦争像が浮かび上がってくるものか。その大切さをとしみじみ思った。
大戦終結百年の報道に中には、フランス、ロレーヌ地方のミュズレー村に侵攻したドイツ軍が放置した毒ガスが百年後の今も土壌汚染を続けているという記事があった。フランスとの国境の町、ベルギーのイーペルで百年前にドイツ軍が放った塩素ガスがもたらした惨状は知られた話だが、そこではいまだに毒ガスの不発弾が見つかり、土壌汚染も深刻だという。忌まわしい思い出に蓋をして「処理」を怠ると、戦争は、精神的にも物理的にも、過ぎ去ってはいかないことをこれらの事実は教えてくれている。
Created by staff01. Last modified on 2019-01-10 16:00:42 Copyright: Default