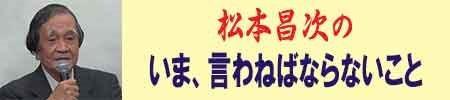第15回 2014.6.1 松本昌次(編集者・影書房)
茨木のり子さんがわたしたちに問うもの

それは、茨木さんの生涯をつらぬく、いまなお天皇制を温存する日本国家への怒りである。詩集『自分の感受性くらい』は有名だが、そこに収められた「四海波静」を一体誰が書けるだろうか。「戦争責任を問われて/その人は言った/そういう言葉のアヤについて/文学方面はあまり研究していないので/お答えできかねます/思わず笑いが込みあげて/どす黒い笑い吐血のように/噴きあげては 止り また噴きあげる」。こんな天皇をかかえて怒るに怒れず、茨木さんも「ブラック・ユーモア」としかいいようがない。こういう作品を展示関係者は、避けて通っているのではないか。

*「茨木のり子展」ポスターなど
会場で販売している茨木のり子展「図録」に、茨木さん没後のすべてを引き受けた甥で医師の宮崎治氏が書きとめているが、あるコンサートのさい「君が代」が演奏されると、誰もが慌ただしく起立するなか、茨木さんは「私は立たないわ」と立たなかったという。それとおぼしき詩が最後の詩集『倚りかからず』にある。
「なぜ国歌など/ものものしくうたう必要がありましょう/おおかたは侵略の血でよごれ/腹黒の過去を隠しもちながら/口を拭って起立して/直立不動でうたわなければならないか/聞かなければならないか/私は立たない 坐っています」(鄙ぶりの唄)。
かつて、このような詩を書いた詩人がいただろうか。この決然とした姿勢こそ、茨木さんの生き方なのだ。
最愛の夫・三浦安信氏が亡くなったあと、50歳でハングルを学び、エッセイ集『ハングルへの旅』、訳詩集『韓国現代詩選』を刊行したことは有名だが、茨木さんは、何も好き好んでハングルを学んだわけではない。詩集『寸志』に収められている「隣国語の森」では、かつての植民地支配時代、日本がハングルを抹殺しようとしたことを詫び、「倭奴(ウエノム)の末裔」として、「美しい言語の森」=ハングルを学ぼうとの決意をのべる。そして、韓国にとっては「光復節」、日本にとっては「降伏節」直前、日本官憲に捕えられ、福岡刑務所で謎の死をとげた、韓国の民族詩人・尹東柱(ユントンジュ)への限りない思慕の思いを、茨木さんは美しい詩句にとどめたのである。茨木さんの詩集全体を貫流する、天皇制国家のかつてのアジア諸国に対する植民地支配・侵略戦争、さらに今なおそれらを根底から払拭できないものへの怒りを忘れてはならない、とわたしは強く思う。
いま、毎日のように、安倍首相は、「国民の命を守るため」などの看板をかかげて「集団的自衛権」云々をわめき散らしている。この人にも、茨木さんの一篇の詩を捧げよう。
「言葉が多すぎる/というより/言葉らしきものが多すぎる/というより/言葉と言えるほどのものが無い//この不毛 この荒野/賑々しきなかの亡国のきざし/さびしいなあ/うるさいなあ/顔ひんまがる(以下略)」(賑々しきなかの)
Created by staff01. Last modified on 2014-05-31 22:23:52 Copyright: Default